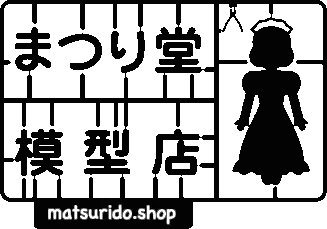街の模型屋の存在意義を考える
2025/08/07
街の模型屋の存在意義を考える
先日、X(旧Twitter)で印象的な投稿を目にしました。
とある個人経営の模型店が、いくつかのメーカーの商品の取り扱いを終了するとの貼り紙を出したというものです。
https://x.com/takaakiget10000/status/1953000589790679301
そこには、「近年の価格高騰により、売れ残った場合の在庫リスクが大きく、経営を圧迫してしまうため」という説明がありました。
確かに昨今、プラモデルの価格は全体的に上昇傾向にあります。原材料費や輸送コストの高騰、製造現場の人件費増加など、背景にはさまざまな要因があると思います。
しかし、私はこの価格上昇を、必ずしも一面的に否定すべきものだとは感じていません。
むしろ、動くお金が増えることで、製造・開発・販売など、プラモデルに関わる人々の労働が正当に評価され、その結果として文化の継続や品質の維持に繋がる面もあると考えています。
また、同じ商品を販売するなら、当然ながら価格が上がったほうが、模型店の収入にも好影響があるはずです。これはごく自然な経済の流れであり、持続可能な模型業界のためには避けて通れない課題とも言えるでしょう。
とはいえ、現場で販売を担う模型店にとって、価格上昇が即座にメリットになるとは限りません。高価格の商品が売れ残れば、店舗側にとっては不良在庫となり、仕入れのリスクはかえって増してしまいます。特に個人経営の店舗では、その影響が経営全体を左右するほどに大きくなることもあり、慎重な仕入れ判断を迫られるのが実情です。
そうした背景から、リスクを避けるために「注文中心」の体制に移行するという選択は、経営判断として理解できます。しかし、それによって店舗に商品が並ばなくなってしまえば、お客様が“現物を見て選ぶ”という楽しみは失われてしまいます。
模型屋の魅力は、やはり陳列された箱を眺めながら、思いがけない出会いを楽しめるところにあると思います。店に行き、思いがけず出会ったキットに心惹かれる──そうした偶然がもたらすワクワク感は、ネット通販ではなかなか味わえません。
注文制になれば、店舗は単なる「受け取り窓口」になってしまいかねません。現物に触れて、語って、選ぶことのできる空間としての価値が失われてしまうのです。
もちろん、全てを在庫として抱えることは現実的ではありません。お店にとっても、限られたスペースと予算の中で、何を並べるかの選別は必要です。それでも私は、街の模型屋が「見る・選ぶ・語る」場であり続けてほしいと願っています。
ストレートに表現するならば、魅力ある商品を目利きして仕入れ、店頭に陳列する努力をすることは、街の模型屋としての責務であり、街の模型屋の魅力の根源であると思います。はばからずに言えば、仕入を放棄することは、その店の存在意義を放棄することとイコールだと思います。
プラモデル初心者が相談できる場所、常連が技術や情報を共有できる場所、そして子どもたちが初めて模型に触れる場所。そんな“場”を守ることは、単に商品を売るという以上に、模型文化そのものを支えることだと思います。
これからの時代、模型店にも変化は求められるでしょう。しかし、その変化の中でも「模型屋らしさ」を失わず、文化と人をつなぐ場所としてあり続けるためには、私たちお客側の姿勢も問われると思います。ときには店に足を運び、商品を見て、会話をして買い物を楽しむ──そんな時間が、街の模型屋を守る力になるのではないでしょうか。