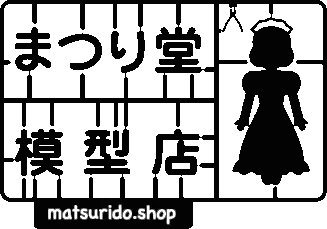「海賊版展示会」騒動に思う ─ 怒りとジョーク、SNSとガンプラ文化の臨界点
2025/09/20
「海賊版展示会」騒動に思う ─ 怒りとジョーク、SNSとガンプラ文化の臨界点
発端は一人のモデラーの怒りでした。
なかなかガンプラが手に入らない状況に苛立ち、その感情を「ジョーク」の形でSNSにぶつけてしまったのです。その言葉は「いっそ海賊版の展示会でもやったらどうか」というものでした。もちろん本人にしてみれば現実的な提案ではなく、あくまで思考実験のつもりだったのでしょう。けれども、その一文は瞬く間に拡散し、強烈な反発を呼び、炎上へとつながっていきました。
ここでまず考えておきたいのは、海賊版とは何かという問題です。海賊版とはメーカーや版元の権利を無断で侵害し、公式を装って複製された非正規品のことです。正規ルートを経ないため品質は保証されず、安全基準も不明で、材質や精度も怪しいものが多い。メーカーにとっては開発費や新商品の企画資金を奪われる存在であり、小売店にとっては正規品の販売機会を失わせる脅威です。
そして最終的には、ユーザーであるモデラー自身が不利益を被ることになるのです。再販や新商品のラインが細り、店が消え、正規の選択肢が減ってしまう。その意味で「売るのも買うのもだめ」というのは単なる道徳的なスローガンではなく、文化の持続可能性を守るための必然なのです。
ではなぜここまで炎上したのか。それは「思考実験」という言葉や前置きが切り捨てられ、「海賊版展示会」という刺激的な断片だけが一人歩きしたからです。SNSでは長文が読み飛ばされ、短く過激な部分が切り抜かれ、引用され、怒りの燃料となります。元々は仮想的な議論であっても、拡散の過程で「本気の提案」に変換されてしまう。発信者が「そんなつもりじゃなかった」と弁明しても、文脈崩壊は止まりません。SNSのアルゴリズムは感情の強い言葉を好み、怒りを拡散させてしまうからです。
背景には、ガンプラをめぐる空気の過敏さがあります。長引く品薄と転売問題の積み重ねで、SNSの世論は極端に敏感になり、「ガンプラが手に入らない」と言うこと自体が炎上の火種になりかねません。実際、少し愚痴を書いただけで「転売擁護か」「乞食行為だ」といった攻撃を受ける例もあり、モデラーたちは本音を語ることを恐れるようになっています。
まつり堂模型店でも、お客様から「再販はありますか」と尋ねられることが、最近はDMや直接来店の場に移り、ガンプラの在庫や入荷予定に関する情報の公開の場での発言は減っています。正直な声が地下に潜ってしまうことは、健全な対話を難しくする大きな問題です。
さらに言えば、メーカー側もネットをよく監視しています。需要を把握し、問題点を見つけるのは当然のことですが、小売の立場からすると不用意な発言が「公式批判」と受け取られかねないため、言葉選びに細心の注意が必要です。だからこそ私たち店側は過激な言葉を避け、できるだけ冷静に事実を伝える姿勢を心がけています。沈黙するのではなく、誤解されにくい成熟した言葉を選ぶことが、小さな店にできる責任だと考えています。
それでも、今回の騒動が示した現実を無視することはできません。新商品が今後も今回のリックドムのように希望した数量どおり入るのかは、正直まったく分かりません。再販品についても、欲しい数がそのまま届く未来が訪れるのかは未知数です。おそらく今後もガンダムベースや大型量販店に商品が集中し、まつり堂模型店のような新規の弱小店は仕入れに苦戦を強いられるでしょう。だからこそ、当店としては「希望した数量が確実に入荷し、欲しい人の手に渡る」という未来を願わずにはいられません。
そして、この流れが転売屋を駆逐するきっかけとなってほしいと心から思います。彼らが市場を歪め、ファンの喜びを奪ってきたのは紛れもない事実だからです。
結局のところ、今回の「海賊版展示会」騒動は、みんながガンプラを愛しているからこそ起きた摩擦だと思います。怒りを抱えること自体は正当です。しかし、その怒りを「海賊版」という最悪の選択肢に接続してしまうのは誤りです。言葉を武器にするのではなく、問題解決のためのツールとして使うことが大切です。まつり堂模型店は、正規品を守りつつ、成熟した言葉でお客様やファンと対話を続け、少しでも健全な文化づくりに貢献していきたいと思います。