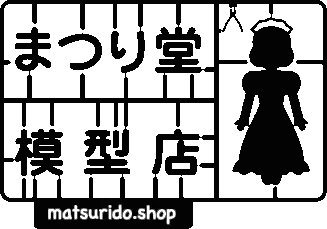書店の苦闘から学ぶ、模型店の未来
2025/05/05
書店の苦闘から学ぶ、模型店の未来
——『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』を読んで考えたこと
先日、新書『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』を読みました。本書は、全国に数多く存在していた“町の本屋”がどのように衰退し、そして消えていったのかを丹念に描いた一冊です。模型店とは業種こそ異なりますが、その内容には、私たちのような地域密着型の小売店が生き残っていく上で大切なヒントが詰まっていました。
たとえば、北海道の「いわた書店」では、店主が読者の好みを丁寧に聞き取り、1万円分の本を選んで送る「1万円選書」というサービスが話題を呼んでいます。これは、Amazonのレコメンド機能とは違い、人間の目と感性で選ぶからこその説得力があり、顧客に“自分だけの価値”を感じさせてくれるのです。このような「提案型販売」は模型店でも応用できます。お客様の経験や興味に応じたキットを選定し、セット販売や定期発送サービスとして提供することで、オンライン通販にはない体験を生み出すことができます。
また、東京・神保町の「姉川書店」は「猫の本専門店」として再出発し、猫好きの聖地として注目されています。書籍の世界でも特定ジャンルに特化することが成功の鍵となるなら、模型店もまた、戦車・鉄道・美少女・ガンプラなど、得意な分野を明確にし、専門性と品揃えで勝負する姿勢が重要になるでしょう。特化することで、お客様との会話の質も深まり、強い信頼関係を築けるはずです。
さらに、大阪の「隆祥館書店」のように、地域の人たちと繋がるイベントやトークショーを継続的に開催することで、書店が“本を買う場所”から“文化を共有する場所”へと進化している例もありました。模型店においても、製作会や展示会、初心者講座などを通じて「人が集まり、語り合う場」としての役割を果たすことが求められていると感じます。
もちろん、情報発信も欠かせません。「さわや書店」などはSNSで選書や店舗の様子を発信し、地元にとどまらず全国のファンを獲得しています。模型店も、完成品の紹介や製作過程、メイドスタッフによるデモンストレーションなど、発信できる素材は豊富です。SNSやブログを通じて、店舗の魅力を広く伝えていくことは、小さなお店が大手と差別化するための大きな武器になるでしょう。
模型店の将来と、いま取るべき対策
今後、模型店はさらに厳しい競争環境に置かれると予想されます。通販サイトの台頭、メーカーの直販強化、価格競争の激化、そして人口減少に伴う客層の縮小――これらはすでに進行中の現実です。
しかし、その中でも地域密着型の模型店には、リアル店舗ならではの「体験」と「信頼」という強みがあります。実物を見て選び、詳しいスタッフと話しながら購入できる喜びは、デジタル化が進んだ今だからこそ、むしろ希少価値を増しています。
生き残るためには、以下のような取り組みが必要になるでしょう。
-
個別対応サービスの導入:お客様のレベルや趣向に応じた「模型セレクトサービス」の展開
-
ジャンルの明確化と専門性の追求:何に特化した店なのかを明示し、深堀りする
-
交流の場づくり:製作会や展示会、講座など、人と人が出会える機会の創出
-
積極的な情報発信:SNSやブログで、日常の一コマから新商品紹介までこまめに発信
-
オンラインとの融合:リアルとネットの連携強化。たとえば、来店者限定の配信やオンライン製作会など