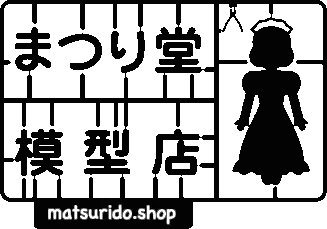コラムから見えたことー鉄道好きが反応した理由を考える
2025/09/01
コラムから見えたこと-鉄道好きが反応した理由を考える
先日、当店のブログで「迷惑なお客様問題」についてコラムを書きました。非常に多くの方にXで「いいね」や「リポスト」していただき、ありがとうございました。
反応してくださった方々のXのポストを丁寧に読ませて頂いたところ、不思議なことに、リポストしてくださった方々の多くが鉄道ファンのアカウントだったのです。これまで当店の記事に鉄道好きの方が大きく反応されることは少なかったので、この現象には正直驚きました。なぜ鉄道ファンが、このテーマに共感されたのでしょうか。
鉄道ファンが抱える「似た構図」
第一に考えられるのは、鉄道趣味の世界においても「一部の迷惑行為」が大きな問題として取り沙汰されていることです。とりわけ有名なのは「撮り鉄の迷惑問題」でしょう。線路内に立ち入ったり、駅員や他の利用者に迷惑をかけたりする行為が報じられると、鉄道ファン全体が「マナーの悪い集団」と誤解されてしまいます。実際にはほとんどの撮影者がルールを守って楽しんでいるのに、少数の行為が大きな影を落としてしまうのです。
これは、まつり堂模型店での“長話迷惑客”問題と非常によく似ています。ほとんどのお客様は良識を持ってご来店、お買い物をして頂けていますが、ごく一部の方が「自分の話」を延々と続け、店全体の雰囲気を固くしてしまう。その結果、初めてご来店されたお客様、模型にこれまでなじみのなかったお客様に「模型店=自分のなじめない場所」という印象を与えかねません。
「語る文化」と共感
第二に、鉄道ファンは「語る文化」を大切にする人たちです。車両の形式、塗装の変遷、運行ダイヤの思い出――語れば語るほど楽しくなるのが鉄道趣味の醍醐味です。その意味で「語る場が心地よいかどうか」には敏感です。今回のコラムの中で、当店が「鉄道や模型の話なら大歓迎」と明言したことに共感が集まったのではないかと感じています。
鉄道ファンからすれば、「自分たちの世界にも似た問題がある」「だからこそ“語る場”を守りたい」という思いが重なったのではないでしょうか。
地域性と鉄道の結びつき
第三に、下関という土地柄も関係しているでしょう。関門トンネルを抜けるブルートレイン、末期色の115系、観光列車「瑞風」――この街には語るべき鉄道の物語がたくさんあります。鉄道と街の記憶が結びつく場所で「鉄道を語れる店」が存在することに、鉄道ファンは親近感を抱いたのではないでしょうか。模型は単なるミニチュアではなく、実際の鉄道の物語を再現する手段でもあります。そこに共感を覚え、リポストした方も多かったのだと思います。
共通する課題と対策
ここで改めて気づくのは、「一部の迷惑行為が全体に悪影響を及ぼす」という点で、鉄道ファンの世界と模型店の世界は同じ課題を抱えているということです。
模型店では、一部の特殊なお客様が他のお客様に迷惑をかけないようにする必要があります。
鉄道趣味の世界では、一部の過激な撮り鉄の行動によって、他の良識あるファンに迷惑が及ばないようにする必要があります。
両者に共通しているのは、「主役は人ではなく対象そのもの」ということです。鉄道の主役は列車であり、模型店の主役は模型です。ところが、一部の行為が“自分自身”を主役にしてしまうことで、本来の舞台が歪んでしまうのです。
対策としては、やはり「ルールと環境づくり」が欠かせません。模型店としては、来店された方が快適に過ごせるよう、話題の範囲をやんわりと提示し、必要に応じて線を引くことが求められます。鉄道ファンの世界でも、主催者や仲間同士がマナーを共有し合い、「楽しく撮るための文化」を広めることが解決の道となるでしょう。
今回のリポストの広がりは、鉄道と模型という一見異なる趣味世界が、実は同じ課題を抱えていることを示す出来事でした。少数の行為に振り回されず、すべての趣味人が安心して楽しめる場を守っていくこと。これは鉄道にも模型にも共通する課題であり、未来へつなげていくべき文化的な使命だと感じています。
まつり堂模型店はこれからも、他の方に迷惑をかける客のいない、模型ファンが安心して訪れることができるお店として、模型を主役にした空間を守り続けたいと思います。